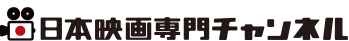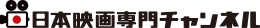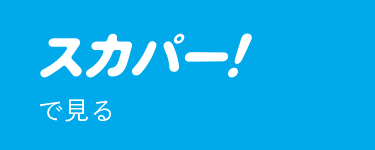■理不尽な場にさらされることが大事
――ところでPFFに参加してみて、映画祭の雰囲気はどうでした?
李:実はあまり行っていないんですよ。本当に申し訳ないことなんですけど。
荒木:当時は忙しかったんですか? 助監督とかをやっていたとか。
李:特に忙しかったというわけではなく。きっと他の作品がどうとか、自分の作品がどう見られているのかとか。そういうことを気にするのが嫌だったんでしょうね。いまだに海外の映画祭でも、お客さんと一緒に見るのは僕にとって拷問なので。そういうことからちょっとでも逃げたかったんだと思うんです。たぶんみんなそうだと思うんですが、人のものはよく見えるんですよ。自分の作品は劣っているんじゃないかという気がして。特に映画で競い合うということに直面したのはPFFが初めてだったんで、なかなか足が向かなかったということはありますね。
荒木:じゃあ表彰式の時はものすごくドキドキした?
李:できれば、行きたくなかった(笑)
――ほかの監督はどうですか?会場には来るんですか?
荒木:半分くらいは毎日のように通ってきて、他の人の作品も全部観ているけど、半分くらいは観ないですね。いろんな人がいますよ。ただ、自分がコンペをやっていてなんですけど、他の映画祭のコンペに自分たちの作品を出してみると、コンペって本当に嫌だなと思いますね(笑)。

――やはり勝負の場だから、ということですかね。
李:勝負のつもりはないんですが、ある種の理不尽がつきまといますね。限られた人たちの主観で映画の優劣が決められるわけですから。でも、必要なことだと思うようにもなりました。PFFのコンペに関して言えば、ほとんどの作り手たちにとって勝負の場にさらされるのは初めてだと思うので、さらされればいいと思います(笑)。他人と自分を比べて苦しんだり、自己顕示欲に嫌気がさしたり、面倒くさい感情に絡めとられれば良いんじゃないでしょうか。とにかく自分にとっての大事なトゲになればいいと思うので。どんどん経験して、どしどしさらされてほしいなと思います。
■応募の際に、PFFスカラシップの存在は大きかった
 李相日監督「BORDER LINE」(C)PFFパートナーズ
李相日監督「BORDER LINE」(C)PFFパートナーズ――その後、李監督はスカラシップを獲得し、『BORDER LINE』を完成させます。
李:やはりPFFに応募しようと思った一番の動機は(PFFが長編映画製作を援助する)PFFスカラシップですよね。卒業制作を一本作ってみて。それを何かの足がかりにするしかないと思った時に、やはりPFFのスカラシップというのは一番大きなチャンスだったんですよ。当時のレギュレーションが「どれかひとつでも受賞できれば、(スカラシップの)企画に応募できる」ということだったので。グランプリでなくてもいいならチャンスがありそうだ、というのが大きな動機となりましたよね。
――そもそもスカラシップはどのようなきっかけで始まったのでしょうか?
荒木:スカラシップが始まったのは1984年でした。今の感覚だと理解しにくいかもしれませんが、当時、8mmフィルムで映画を撮るということは、子どものおもちゃで撮るようなものだったんです。そこで無理矢理長編を撮った、先ほど名前の挙がった石井聰亙(現・石井岳龍)みたいな爆発する映画熱のようなかたたちがいて、そういう時代にプロを目指して次の段階に行くということは、今とは比べものにならないくらい、ものすごくハードルが高いことだったんです。だからそういった8mmの映画監督と、撮影所から出てきたプロとが一緒に映画を作ったらすごいことが起きるんじゃないか、というのがスカラシップのはじまりなんです。最初はプロと一緒に商業映画の35mmフィルムは無理だけど、16mmフィルムを使って映画を作るということだけが大事だったんですけれど、だんだんそれだけでは済まなくなって。出資を募ったり商業的ヒットも求められるようになったり。その性質もどんどん変わっていきました。
 荒木啓子 PFFディレクター
荒木啓子 PFFディレクター――スカラシップの権利を得るのは、その年のPFFアワードでグランプリを獲得した監督だけでなく、その他の賞を獲得した監督にもチャンスが与えられます。企画を提出して、それが選出されれば映画制作の援助をしてもらえることになります。
荒木:スカラシップは単なる援助ではなく、トータルプロデュースなのです。最初は雑誌ぴあのお金で映画祭スタッフが選んだ人のプロデュースでした。第1回スカラシップは当時高校生の風間志織監督が選ばれて、『イみてーしょん、インテリあ。』を作りました。その後も斎藤久志監督の『はいかぶり姫物語』などが続きましたが、それまでコンペティションシステムではなかった、「自主製作映画部門」として入選作品しかなかったPFFが「PFFアワード」としてコンペティションになったのが1988年。そのときから、グランプリ=PFFスカラシップ獲得になったのです。そうすると「やりたいことがありません」と言って、降りる人も出てきた。「スカラシップを取ったら絶対にこれをやるんだ」という人ばかりではないなという現実があり、そこからいろいろと考えて、賞を取った人はみんなにチャンスがあるという形にしました。でもそれが2018年にもなると、そういったチャンスはまわりにゴロゴロと転がっていますよね。そうすると時代と共にPFFスカラシップの意味も変わってくるんだと思います。では、現代のPFFスカラシップとは一体何なのかということは、常に課題です。