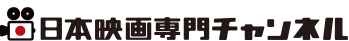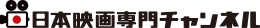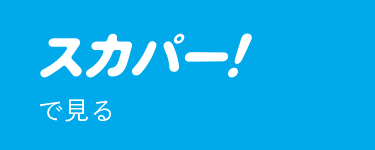■結束の固いスタッフが映画祭を支えてきた
――そんなPFFも今年で40回目となりますが。
荒木:もともとが自主制作で映画を創る人たちをもっと知らしめたいという思いから始まった映画祭なので、それを今までひたすらやってきた。それ以外に何の欲もなかったから、映画祭がここまで続いているのかもしれませんね。
――とはいえ、この規模で定期的にやり続けるのはすごいことだと思います。
荒木:その辺は自分では分からないですけどね。プログラムを作っているのはひとりだし、現場スタッフは合計4人しかいないし。ここで貧乏自慢をしてもしょうがないですけどね(笑)。
李:でも、規模が大きくなりすぎた映画祭が、何かひとつの発火点をきっかけとして内部がガタガタと崩れることがあって。そういう事例を目の当たりにすると、PFFのようなファミリービジネスというか、ファミリー映画祭は結束が固いなと思いますよ。
荒木:ファミリービジネス? ビジネスにはなってないけどね(笑)
李:「荒木一家」みたいな感じですよね(笑)。自分たちが大事にしているもの、大切にしているものを残すギリギリの形なのかなと思うんですけど。これでディレクターが3人いて、スタッフが数十人いてという形になった時はどうなるか分からないですけどね。
荒木:確かに手作り感満載の方がいいかもしれないですね。
李:それがPFFの特色というか、精神性の強さを感じますよね。そしてそれを生み出しているのが不撓不屈のメンバーたち、“荒木一家”ですからね。僕がグランプリをとってから18年が経ちましたが、関係性や距離感が変わらないのはPFFだけですね。僕なんかはPFFを出たくせにあまり力になれなくて申し訳ないですけれども。でもちょっと離れたところから見ていてもその存在感は変わらないというか。そこにあり続ける灯台みたいな感じですよね。ここまで続いたからこそ、戻る場所があるんだと思います。

――近年の応募状況はどうでしょうか?
荒木:出身地は全国まんべんなく広がっていても、住んでいるのは東京という人が多いですね。神奈川や埼玉を含めると、日本の人口の3分の1は関東圏に集まっているので、それはそうだろうなとは思いますが。それから関西、九州など、PFFを開催している地域の学校から応募する人もいますが、それでも卒業したら東京で働くという人も多いですよね。つまり、東京に映画映像の仕事が集中してきているんですね。こうした東京一極集中というのもよくないなと思っていて。映画が面白くなくなっちゃいますからね。
 本年は、529本の応募から18本の作品が入選
本年は、529本の応募から18本の作品が入選この中からグランプリを含む各賞が選ばれる
李:去年、審査員をやってみて、ちょっと感じたことなんですが、自分の感情や思いをうまく整理できているなと。それこそ僕が最初に抱いていたザ・PFFとも言うべき、“異能”たちの情念の爆発や葛藤の垂れ流しが減ってきた。本来、PFFが持つエネルギーって、ある種行き場のない感情や思いが映画に詰め込まれていたからこそ、映画界に地殻変動を起こしていた気がするんです。まさに映画祭のプログラムにも、もっと泥まみれになりなさいという荒木さんのメッセージが根底にあるような気がするんですよね。今は上手に作らなきゃいけないということが傍目には求められているとは思うんですが、それ以前にもっと大事なものがあるんじゃないか、ということをぶち込もうとしている気がしますけどね。
荒木:ありがとうございます。
■特集上映は応募者や入選者に観てもらいたいことが基準
李:特集上映に関しては荒木さんとスタッフで話し合って決めているんですか?
荒木:いや、これは私が決めています。
李:荒木さんの独断と偏見で?
荒木:いやいや、独断と偏見じゃないですよ(笑)。PFFアワードの応募者や入選者に観てほしいということを基準にプログラムは作っています。そこが他の映画祭とは全然違うところですよね。彼らがこれを観ることによって、作品が豊かになるんじゃないかと思うことがプログラムを選ぶ基準なので。それは全然変わらないですよ。
李:それだけでも僕は映画祭に行くべきだったと。今ごろになって感じましたよ(笑)。
荒木:例えば今回の特集で上映されるロバート・アルドリッチ監督の作品なんて先の見えない映画ばかりですからね。もっと先の見えない映画を作って欲しいんですよね。最近は本当に先が読めすぎる映画ばかりだから。
李:本当にその通りだと思います。よく監督を、「作家性の強い監督」と「エンタテインメント性の強い監督」に分かり易く区別したがりますが、本当にくだらないですね。生きることと同じで、先が見えないことこそが、そして次にどうなるのか分からないことを追いかけていくことこそが映画の醍醐味じゃないかと。映画を区分けしてしまうなんてつまらない発想だなと思いますよ。だから…入選時に観るべきでしたね(笑)。
荒木:今からでも遅くないですよ(笑)。忘れ去られかけてはいますが、1950年代、1960年代のアメリカ映画というのは世界中から集まってきた人が競って、すごいものを作っていた時代だと思いますよ。今、スクリーンで観るのはとても難しい作品が多いですからね。
■第一線で活躍する人たちの思いを伝えるプログラム
――今年のプログラムはいかがですか?
荒木:今年は面白いプログラムになったと思いますよ。今回、新作はPFFアワードの18作品だけで、それ以外は時代をさかのぼって。時代時代の革命者たちに焦点を当てる映画ばかりなんですよ。
――その他のプログラムについても教えていただければと。まずは「映画のコツ」ですが。
荒木:この特集は、15年ぐらい前からタイトルを変えながら続けているものなんですけれども、第一線で活躍する人たちが、「なぜ自分がこの映画を人に見せたいと思うのか」「なぜ自分がこの事を多くの人たちに知ってもらいたいのか」ということを上映後に対談講座形式でお話していただきます。これを見ることで、きっと得ることがあるはずだという気持ちで続けています。客席からの質疑応答も行います。
 香川まさひと監督「青春」
香川まさひと監督「青春」――「香川まさひとの世界」では、吉田大八監督が登壇します。
荒木:これは吉田さん学生の時、1983年に、PFFで『青春』という4分の短編映画を観て、あまりにも衝撃を受けて、それ以来いろんな人にすごい作品がある、すごい天才がいると言い続けてきたんですね。だから吉田さんはいつか香川さんと一緒にお仕事をするのが夢だったと。遂に26年後に『クヒオ大佐』(2009)の脚本をやってもらおうと、PFFに香川さんの連絡先を問い合わせたと。吉田さんの香川さんへのその熱い想いを以前伺っていたのが、本年、35年を経てこうして多くの方に香川さんを紹介する企画として実現しました。
――まさに吉田監督念願の企画だったと。
荒木:人生、何が起こるかわかりません。おふたり盛り上がっちゃって。とうとう香川さん、新作を撮っちゃった。今回はそれもお披露目します。私もあこがれ続けた天才を世間に知らしめたいという吉田さんの情熱に打たれちゃって。そしてこの日は、香川作品の主演を多く務めた気象予報士の木原実さんもゲスト来場予定になっています。
――「天才・木下惠介は知っている その2」は昨年に続いての登場です。
荒木:原恵一監督と橋口亮輔監督のお二人は、木下恵介ほど偉大な監督はこの世にいないと敬愛の深いお二人です。なのに世間では忘れられているということに対してのお二人の危機感は高まるばかりですので、昨年の回終了後「これは毎年やりましょう」と継続を決めました。そしたらなんと今年は『野菊の如き君なりき』と『笛吹川』という超ゴージャスな二本立て企画になってしまいました!お二人の毒舌トークも楽しみです。
――「本当にみたいテレビ番組創作術」は、テレビディレクターの稲垣哲也氏と佐々木健一氏による講座になります。北野武ドキュメンタリー「たけし誕生~オイラの師匠と浅草~」を参考作品として上映するとのことですが。
荒木:かつてこのプログラムでは、いわゆる映画業界ではない人たち。写真家とかデザイナーとか、アニメーション作家とかテレビドキュメンタリー監督など、多方面の方々をお招きしてきたのですが、今回は久しぶりにテレビの人をお招きします。というのも、現在映像の就職先として、明確にみえる道だからです。稲垣さんは、大学時代に映研で自主映画を作っていてPFFもよくご存知でした。卒業後映像で食べていこうということで、テレビの制作会社に入るわけですが、自分の企画をなんとか実現させたいと思った時に相談するのが佐々木さんということで対談が実現しました。テレビの中で何を作っていいのか、ということは多分映画とはまた別の葛藤があるわけで。そういうことに対するテレビ制作会社の人たちの話というのは、一度やってみたかった企画です。